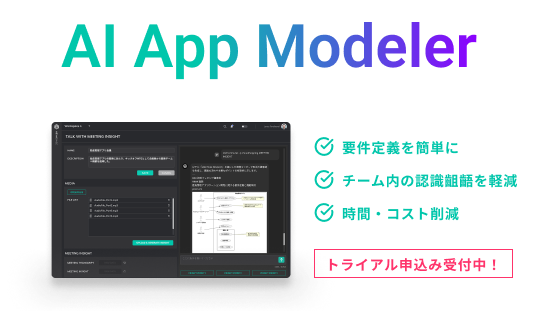COLUMN
2023年04月27日
ChatGPTに教えてもらった!新規事業担当者が知っておきたいSWOT分析の活用術
カテゴリー:ビジネス, 新規事業開発
タグ:DX, 基本用語
新規の事業開発に携わっているとよく耳にするのが、SWOT分析というキーワードです。知っていても、どんなふうに活用すればいいのか、具体的な方法を理解していない人も少なくありません。生半可な理解で真似している人もよく見かけます。
そこで、SWOT分析とは何なのか、具体的な例といっしょにできるだけ分かりやすく説明します。
※この記事は、ChatGPTの回答をライターが30%ほどリライトしています。
SWOT分析とは何か
SWOT分析(スウォット分析)は、ある目的を達成するために、自分や自分が属する組織や企業の課題を内部環境/外部環境、目標達成の助けになる/妨げになる要因に分けて分析する手法です。内部環境を強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)に、外部環境を機会(Opportunities)と脅威(Threats)を4つに分類することから、頭文字をとってSWOT分析と呼んでいます。
SWOT分析で重要なことは、2つあります。
まず、目標達成の助けになる・妨げになることに範囲を絞ること。範囲外のことまで考え始めると発散してしまいますし、キリがないからです。
また、内部環境と外部環境の両方を分析すること。内部環境だけ考えていても、外部に影響を及ぼす戦略を立てるのは簡単ではありません。外部環境に振り回されていては、自分たちの得意・不得意を発揮できません。内部環境と外部環境の両方が重要なのです。
この分析を通じて、自分たちの強みを活かし、弱みを改善すると共に、外部の機会を生かし、脅威に対処する戦略を立てることができます。
内部環境と外部環境の例
ものすごく分かりやすい例として、転校する小学生を例にしてみましょう。
内部環境
- 強み:算数が得意。友達と仲良くなれる。
- 弱み:運動が苦手。宿題を忘れてしまう。
—
外部環境
- 機会:新しい学校で今までと異なる出会いがある。新しい体験や活動ができる。
- 脅威:勉強のレベルが異なる。周囲に馴染めないかも。
—
このようにSWOT分析を行うことで、自社の状況を客観的に見つめ、事業改善や目標設定につなげられます。
小学生の例は子供っぽいと感じるかも知れませんが、入社や転職、新しいビジネスのチャレンジでも同様の内部環境と外部環境が考えらえるでしょう。
SWOT分析のメリットとデメリット
SWOT分析は、新規事業開発や事業戦略・プロジェクトの立案どの立案に用いられる定番の分析手法ですが、次のようなメリットとデメリットがあると言われています。
メリット:
- 総合的な分析: SWOT分析は、内部要因(強みと弱み)と外部要因(機会と脅威)を同時に評価するため、企業やプロジェクトの状況を総合的に把握できる。
- 意思決定の支援: SWOT分析を通じて得られた情報は、経営者やプロジェクトマネージャーが戦略を立てたり、リソースを最適に配分する際の意思決定を支援する。対応策をただ提案するだけでなく、その提案に至った理由の論理的な説明に役立つ。
- コミュニケーションの促進: SWOT分析は、チームメンバーや関係者間で情報や意見を共有し、意思疎通を図ることができる。SWOT分析の結果を共通言語として用いることで、組織全体の認識の統一を促進できる。
—
デメリット:
- 主観性: SWOT分析は、評価者の主観やバイアスが結果に影響する可能性がある。そのため、分析結果の信頼性や客観性が低下することがある。
- 静的な分析: SWOT分析は、ある時点での企業やプロジェクトの状況を評価するため、状況が変化すると分析結果がすぐに陳腐化することがある。
- 優先順位の欠如: SWOT分析では、強み、弱み、機会、脅威の要素がリストアップされるが、それらの要素の優先順位や重要度が明確でない場合がある。そのため、意思決定や戦略立案において迷いが生じることがある。
—
このようなメリットとデメリットがあるため、SWOT分析は万能の戦略ツールとはなりません。企画立案や議論を進めるときアイデア出しなどの場面で役に立つでしょう。
SWOT分析の進め方
では、SWOT分析はどのように進めればいいのでようか。一般的に、次の手順で進めると良いとされています。
ステップ1. 目的とスコープを明確にする
まずは、SWOT分析の目的とスコープを明確にします。自分や自分が属する組織や企業が何を達成したいのかを明確にてメンバーで共有しましょう。
先ほどの小学生の例では、「転校する小学生が新たな居場所を確保する」といった目的になります。
ここを同意しておかないと、議論が発散して何を検討しているのか分からなくなってしまいます。
ステップ2. 内部の強みと弱みを洗い出す
自分が属する組織や企業の内部に目を向け、強みと弱みを洗い出します。自分自身の場合は、自分の得意なことや苦手なことを考えてみましょう。
小学生の例では、得意な教科や友達と仲良くなれる、運動が苦手といった特長が内部環境になります。
ステップ3. 外部の機会と脅威を洗い出す
次に、自分や自分が属する組織や企業が直面する外部の環境を見て、機会と脅威を洗い出します。自分自身の場合は、友達や学校、家庭など、自分の周りの状況を考えてみましょう。
小学生の例であれば、新しい学校で今までと異なる出会い、新しい体験や活動が機会になります。異なる勉強のレベル、周囲に馴染めないかもといった脅威が考えられます。
外部環境の分析には、社会情勢を把握するPEST分析やマーケティング分野で使われるファイブフォース分析などが役に立ちます。
ステップ4. SWOTマトリクスを作成する
洗い出した強み、弱み、機会、脅威を、それぞれの要素ごとに整理して、SWOTマトリクスを作成します。
ステップ5. SWOTクロス分析により戦略を立てる
最後に、洗い出した情報を基に、目的を達成するための戦略を立てます。この戦略は、自分自身を改善するためのものであったり、組織や企業の事業戦略であったりすることがあります。
SWOTマトリックスの作成方法
SWOT分析では、内部環境と外部環境について、目標達成の助けになるプラス要因と目標達成の妨げになるマイナス要因を組み合わせた表を作成します。これをSWOTマトリックスと呼びます。それぞれの組み合わせが、強み・弱み・機会・脅威に対応しています。
先ほどの転校する小学生の強み・弱み・機会・脅威をこの表に当てはめると次のようになります。
まずは、このマス目ごとに対応策を考えます。
SWOTクロス分析で戦略を考える
でも、これだけでは「強み・弱み・機会・脅威に分けて考えましょう」というだけになってしまいます。SWOT分析ではこれをさらに進めて、次のようなクロス分析をおこないます。内部環境である強みと弱みと、外部環境である機会と脅威を組み合わせて戦略を考えるのです。これにより、複数の課題を同時に解決できる対応策を立案しやすくなります。
転校する小学生の例では、次のような対応案が考えられます。
自分の強み x 機会:
「算数が得意」かつ「異なる出会い・体験の機会がある」
算数やゲームなど得意な事に関連したクラブやイベントがあれば、積極的に参加して、同じような興味を持つ友達を増やすといった行動を取ります。
自分の強み x 脅威:
「算数が得意」かつ「レベルが異なる(高い・低い) 」
算数が得意でも周囲のレベルが高ければ、ライバルを一緒に学習する仲間にします。
算数が得意でも周囲のレベルが低ければ、勉強をサポートしたり宿題を一緒にするといった行動を取ります。
自分の弱み x 機会:
「運動が苦手・宿題を忘れる」かつ「異なる出会い・体験の機会がある」
同じく運動が苦手な仲間や宿題を忘れがちな仲間と積極的に活動します。
自分の弱み x 脅威:
「運動が苦手・宿題を忘れる」かつ「レベルが異なる(高い・低い)」
運動が苦手なのに、スポーツが盛んな学校に転校してしまった場合、まずは運動能力の改善に取り組む必要があるでしょう。同じようなレベルの仲間と一緒に活動したり、友達と仲良くなれる面をいかして応援を盛り上げたりしても良いでしょう。
特に「自分の強み x 機会」は、自分が能力を発揮しやすいので積極的に攻めるといいでしょう。また「自分の弱み x 脅威」は自分の能力を発揮しにくい箇所なので、しっかりと守りを固める必要があるでしょう。
SWOT分析は、比較的取り組みやすい分析ツールです。こうした枠組みに合わせて情報の整理と対策立案を進めることで、効率よく企画を進められます。ビジネスやプロジェクトの企画立案などで、考えがはっきりしないとき活用すると役に立つでしょう。
参考になるページ
- マンガでわかる「SWOT分析」 | 経済産業省 中小企業庁
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/16748/ - SWOT分析 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/SWOT%E5%88%86%E6%9E%90